C05-硫黄島と東条英機/映画『硫黄島からの手紙』より
太平洋戦争の激戦地「硫黄島」。米軍死傷者が日本軍を上回った唯一の戦場である。 その死闘を描いた話題の映画『硫黄島からの手紙』には、凄惨な自決シーンが描かれている。開戦時の首相であった東条英機の、「日本兵は捕虜になるな」という訓戒が引き起こした惨劇だった。
* *
戦局は悪化の一途だった戦争末期、ついにサイパンも陥落し、本土への直接攻撃は避けられない情勢となる。
迎え撃つ日本軍の最後の防波堤は、東京の南1200キロに位置する硫黄島であった。
現在も東京都小笠原村に属するこの島には、栗林忠道中将率いる2万1千の守備隊が詰めていた。彼らに生きて帰る希望はない。一日でも長く米軍を食い止めるのが、使命だった。
栗林は、地下壕に立てこもる持久戦を企てる。
連日の穴掘り作業に、下級兵は不満をもらし、側近の幕僚までが、
「どうせ死ぬのだから、華々しく死ねばいいのでは」
と訴える。しかし、知略家の栗林はこれを一蹴、全長18キロに及ぶ地下壕を建設して待ち受けた。
2月16日、ついに米軍が上陸作戦を開始する。援軍の望みも退路もない栗林は、敢えて自決を禁じ、最期は、米兵と差し違えよと厳命した。
しかし、弾尽き、負傷し、米兵の火炎放射で丸焼けにされるよりは、と上官の指示を無視して、自決を選んだ者が多かったことが映画に描かれている。
暗い地下壕の奥で、「靖国で会おう」と言い、手榴弾の安全弁を抜く。叫び出したくなる衝動を抑え、一人ずつ、「天皇陛下、万歳!」と叫ぶや、ヘルメットにスイッチをたたきつけ、手榴弾を抱きかかえるのである。
そんな日本兵の遺骨が今なお回収されぬまま、多数残っているといわれている。
■戦陣訓
彼らを自決に追いやった原因の第一は、〝死ねば靖国の神になる〟という鬼神信仰である。
日本神道では、死んだ人畜の霊が神社などに留まり、生きている人に禍福を与えるという。これを仏教で〝鬼神〟といわれる。戦争で死ねば英霊として「靖国」の神になれるとされ、若者を戦争に駆り立てた。
もう一つの原因は、昭和16年、陸相時代の東条英機が軍人の行動規範として公布した『戦陣訓』である。いわく、
「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」。
〝捕虜となるよりは、潔く自決せよ〟というこの文書の影響で、かなりの軍人が、自決を美徳と考えていた。
当の本人の東条英機も敗戦後、
「自分は、皇室及び国民に対して最も重大な責任がある。このお詫びは死をもってするほかない。」
「戦争中に自分が公布した戦陣訓中の一句―俘虜の辱めを浮くるよりも死を選べ―を自ら破ることはできない」(上法快男編『東条英機』)
と自決の意志を固め、東京都世田谷用賀の自宅で時機をうかがっていた。
頭を射抜くのが、いちばん確実な自決の方法だが、GHQは遺体を写真に撮るだろうと推測し、遺体の見た目も大事にしたいと考えた。
自宅向かいに住んでいた医者に頼んで、心臓の位置に墨で印をしてもらい、自決した娘婿が使った軍用銃を携帯して、いつでも撃てるようにしていた。
■自決失敗
敗戦から約1カ月たった9月11日午後4時2分、アメリカ陸軍中佐一行が、東条邸に急行した。
戦犯の召喚は普通、日本政府を通じて書面で交付されたが、これは異例だった。しかも、新聞記者を多数、帯同している。正式な逮捕ではないと直感した東条は、観念した。
銃声と同時に踏み込んだ憲兵が確認すると、弾は心臓をかすっただけで肺を貫通し、一命を取り留める。
20年12月8日、傷が完治すると、野戦病院から巣鴨の刑務所へ移された。
エリート軍人として駆け上がり、抜群の記憶力から「カミソリ東条」と呼ばれ、独裁内閣を築いた。戦争が、赫々たる戦果を挙げていた時は、騎虎の勢いだったが、一敗地にまみれ、A級戦犯の筆頭として、板敷きの上にワラ布団を置き、毛布五枚のほか、何も持ち込めない刑務所の独房にぶちこまれるや、かつての総理大臣、陸相、参謀総長、内務、文部、軍需、外務の各大臣を歴任した威厳は微塵もなく、孤影悄然たる姿に、人間本来の実相を見せつけられた思いをしたことであろう。
人間のつけた一切の虚飾を、ふるいおとされたそこにあるものは、かよわき葦のような罪悪にまみれた自己でしかないのである。
■汗まみれの聞法
戦犯の九割が仏教徒だったので、浄土真宗の花山信勝(しんしょう)氏が、教誨師として法話をすることになった。
21年6月下旬、急ごしらえの仏間で始まった法話に現れた東条は、丸腰の軍服姿にトレードマークの眼鏡が光っていた。
花山氏の回想によれば、その日、東京の温度は32度以上の暑さだった。窓が一方にしかない仏間には風も入らず、蒸し風呂のような中、東条は扇子も使わず、身動き一つせず、真剣に聴聞した。顔から汗がダラダラ流れ落ちても、ハンカチでぬぐおうともしなかった。
その真剣さに引きずられて、花山氏も汗まみれで法話を続けたという。
それまでは、全く真宗の教えに疎かった東条も、獄中で『正信偈』をよく拝読し、こう語っている。
「ことに大無量寿経は偉いことですね。その中でも殊更に、(阿弥陀如来の)四十八願を読むと、一々誠に有り難い」
「この『正信偈』の中には、信ずるということを、何べんも繰り返していわれているですね。初めには応信如来如実言、終りには唯可信斯高僧説、その他お話の中にもあったように、信ということをくどくどいっておる。有り難いですなぁ。私のような人間は愚物も愚物、罪人も罪人、ひどい罪人だ。私の如きは、最も極重悪人ですよ。本当の仏様の目から見れば実に極重悪人ですよ。例えば肉を食うとか、米を食うとか、米にも生命がありますよ。そういう食事のことからだけ考えても、それらを食わねば生きて行けない人間だということは、全く極重悪人です。それがよくわからないと、極重悪人がわからない。ちっぽけな智慧、それが禍いしてくるのですね。だから、知識人は信仰に入れないのですね。この間私はある書物を読んだのですがね。シベリアに住んでいる人なんですが、樹を見ても泣いたり、呼吸したり、くさみをしているようにも見え、そこら中のものが、みな自分と同じように生きている。そういうふうに、自分たちの周囲をながめているのですね。ものの見方が違って来たのです。すべて人生ということを中心にしてこれを見るというふうに……首切られる時は御聖教も正信偈もいけない。ただ南無阿弥陀仏以外にない。人間は、生死を超えなければいかんですね。」(『巣鴨の生と死』花山信勝・著)
「個人からいえば、
一、宗教に入り得たということ。
二、人生を深く味わったということ。
三、それに裁判において、ある点を言い得たということ。は、感謝しています。」
花山氏は東条の様子をこう記している。
「その後、一ヶ月余りの期間に、七、八度面談したが、その都度、罪悪深重の自己反省、阿弥陀仏救済の法悦、その法悦の境地へ家族の人たちを勧誘せんとの念願を漏らされ、地上平和の建設には宗教心の絶対必要のことを繰り返し繰り返し説かれたことであった。また、仏説の真実、極楽の実在、政治と宗教、軍人教育と宗教、仏教と神道との関係、青少年の教育、戦死戦災者及びその遺家族の救護、戦争放棄と将来の国策、追放者及び拘置受刑者に関する問題等についても、意見を述べられた。」(『亡びざる生命』花山信勝・著)
■敵国の仏縁念ず
法悦は、相手の仏縁を念じる心となっていった。面会に来る家族にはもちろん、アメリカ人へも及んだ。
ある時、米軍将校の左手と手錠でつながった自分の右手を見ながら、花山氏に語っている。
「初めは、これがいやだったんですね。(中略)今では、これもいいと思ったんですね(中略)わたしがこうして、手を合わして仏を拝むと、この人(隣の米軍将校)も手を挙げて拝んでくれる。今、アメリカに仏法はないと思うが、これが因縁となって、この人の国にも仏法が伝わってゆくかと思うと、これもまたありがたいことと思うようになった」(『巣鴨の生と死』より)
初めは、皮肉かと思ったが、東条の顔つきは、大まじめだった。深い宗教体験からの自然発露であったのだろうと氏は回想している。
■死の十三階段
昭和23年12月22日深夜。東条英機らは、廊下で立ったまま、花山氏と最後の勤行をする。仏前からお下げした葡萄酒を紙コップで飲み干した東条は、
「ああ、うまかった」
と満足げに言い、刑場に入るまで、
「南無阿弥陀仏、
南無阿弥陀仏」
と声高に称えていたという。
弥陀の浄土へ往生できる喜びをつづった歌が3首残されている。
○さらばなり有為の奥山
今日越えて
弥陀のみもとに
往くぞうれしき
○明日よりは
誰にはばかるところなく
弥陀のみもとで
のびのびと寝む
○日も月も
蛍の光さながらに
行く手に弥陀の
光輝く
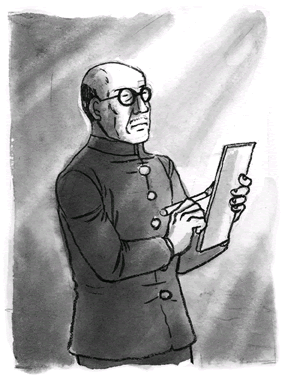
「この二番目の歌は、すぐそのあとで、
『百燭光を昼も夜もつけているので、よくまあ神経衰弱にならなかったものと思う、信仰のあったお陰です』
といわれた。判決があってから最後の日まで、約四十日のあいだ、昼も夜も、三畳敷き位の独房に、百燭の大きな伝統がともっていた。そこであかるいからと毛布をかぶってねていると、すぐに鉄扉の錠がはずされて毛布がはがされた、というわけだから、無理からぬ。前晩、宣告の時苦情の一つに言われた。
『われわれは日本人だから、大便や小便をしているときまで監視されたのは、いい感じではなかった』
と。
自殺しないようにと監視する立場からは止むを得なかったとしても、監視されるものにとっては耐え難かったと思う。そこで『明日よりは、誰にはばかるところなく……のびのびと寝む』になったのもうなずける。
これだけの歌を聞くと、東条という人は、自分だけそういった心境に達したのはよいが、残された我々をどうしてくれんだ、息子を戦死させられたり、父親を亡くしたり、大事な主人を失ったりした気の毒な人たち、ことに二千六百年栄えてきた日本をこんなにしてしまって……と。こういうふうに考える人も、もちろん少なくない。ところが、東条大将は、右の和歌のすぐあとに、
われ往くもまたこの土地に還りこむ
国に報ゆることの足らねば
の一首に残された。そして、
『これは仏さまとなってから帰って来るつもりです。還相廻向ですよ』
と付け加えられた。
自分の命令で戦争となり、そして汚した此の国を、どうかして早く再建しなければならぬ。立派な平和な国日本を、宗教国新日本を、そして世界平和を建設しなければならぬ、と。」
「わたしが口の中で「南無阿弥陀仏」と称えたところ、東条大将はことに声高く「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と称え出された。かくして、自然に一歩一歩、念仏の声とともに、刑場入り口まで、うす暗い中庭一町ばかりを進んだ。
『刑場の入り口まで』という指令であったので、チャプレン・ウォルシュとわたしは隊伍を離れ、入り口の扉のところで、この四人の大将たちともう一度シッカリ握手のなかに、『どうか、しっかり』とはげましながら、後姿を見送った。その時、四人とも、腰をかがめて扉をくぐりながら
『先生、あとをどうかよろしく。家内をたのみます。先生もお大事に』
と、最後の言葉を残された。
このときはじめて、臨時構築の刑場の内部をチラッと見たが、皓々たる電燈の明るさで、今しがた歩いてきた中庭とは雲泥の差であった。
四人は、四列に分かれて、別々の十三階段を念仏を称えながら登られた。絞首の綱の長さは、四人の首の高さに応じて準備されていたという。そして足下の板が抜け落ちる最後まで、「南無阿弥陀仏」と称えていたと、あとで米軍将校から聞いた。
東条大将が生前、巣鴨の仏間でいっていられたことを思い出す。
『先生、いまは「正信偈」や「歎異鈔」を読ませてもらって喜んでおるけれど、いざという時には念仏だけだという尊い体験をさせられますね――』(『亡びざる生命』より)
と。
日本と世界を巻き込んだ悪夢から醒めた彼は、大罪を犯したが、多生にも億劫にもあい難い、弥陀の本願を聞けた法悦に満ちている。
翌23日午前零時1分、絞首台に勇んで立っていったという。
◆睡眠不足だった東条
死刑執行前に自殺されては、裁判した意味がなくなると思ったか、GHQは、判決から執行までの約四十日間、東条の独房に、昼夜を問わず、こうこうと明かりを灯した。
まぶしくて毛布をかぶって寝ていると、すぐ米兵がやってきて毛布がはがす。東条は、何度も苦情を述べたが、聞き入れられなかった。
「よくまあ、神経衰弱にならなかったと思う。信仰があったお陰です」
と、花山氏に述懐している。
◆人生の根本問題
日本を不敗の神国と信じ、世界を相手に宣戦した大立て役者が東条英機であるが、獄中で次のように述べている。
「私は宗教としては仏教だ。(中略)仏教の信仰というのは、人生の根本問題に触れることであって、人生の根本問題が決定してから後、社会のいろいろの上っ面なことが解決されてくるのです。自分は神道は宗教とは思わない。私は今、『正信偈』と一緒に『三部経』を読んでいますが、(中略)今の政治家のごときは、これを読んで、政治の更正をはからねばならぬ、人生の根本が説いてあるのですからね」(『亡びざる生命』)
